今回は具体的な投資法、株式や投資信託に解説していきます。
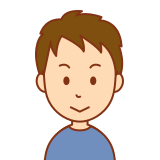
30代医師のトトえもんです。勤務医です。
前回の記事では若手医師の資産形成全般について説明してきたよ。
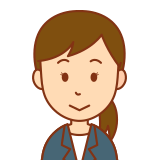
株とか投資信託ってどんなものか知りたいなぁ
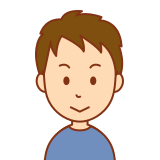
株/投資信託のメリットデメリットについて説明していくよ
株/投資信託での資産形成のメリット
株/投資信託は購入しやすい
株/投資信託は証券会社、特にネット証券などですぐに購入が可能です。
また、上場された株式や純資産総額の大きい投資信託は流動性が高い場合が多いです。
一方で不動産投資となると投資するまでのステップが多く、
しばしば銀行からの融資も必要となるため容易ではありません(逆に参入障壁が高く旨味があるとも言えます)。
株/投資信託は売りやすい
株や投資信託は購入しやすいため、
同時に売りやすいです。
これはいざ現金が不足した場合に簡単に現金化できるという大きなメリットです。
また万が一株価や投資信託の値段が暴落した場合にも迅速に対処できるでしょう。
これを流動性が高いと言います。
上場している株や投資信託(ETF含む)は証券会社などを通じて多くの顧客が売買可能です。
そのため、資本金を調達したい企業は上場して、株を発行して多くの顧客に買ってもらうことで
資金調達します。
インデックスファンドがある

これは投資信託(ETFを含む)の大きなメリットです。
インデックスファンドは株式の指数 (例 S&P 500やNASDAQ 100)に連動した運用を目指すETFや投資信託を提供しています。
また手数料が安いインデックスファンドが多くあります (0.03%前後から0.2%前後まで)
S&P 500に連動したETF VOOやNASDAQ 100に連動したQQQ、CRSP米国総合指数に連動し、アメリカの3000社以上の株式が含まれるVTIが有名ですね。
これらのインデックスファンドのETFや投資信託は自動でファンド会社が
その指数に合わせて銘柄を変更してくれるので、銘柄を選ぶ手間が不要です。
また、インデックスファンドは長期ではアクティブファンドに勝つことが多いとされています。
インデックスファンドとアクティブファンドの説明はこちらをどうぞ
株/投資信託での資産形成のデメリット
借金をして投資はできない
不動産と違い借金をして投資ができません。(レバレッジをかけられない)
レバレッジETFという特殊なETFはありますが、投資上級者向けで、これから投資を始める方にはオススメできません。
レバレッジETFは通常の指数などを指標としたインデックスETF等で指標に合わせて数倍の値動きをするETFです。
AppleやMicrosoftといった情報セクターの株式の構成割合の多いETFがQQQやVGTですが、これらのETFの3倍の値動きをするのがTECLです。
リンク先の株価の推移をみるとQQQやVGTと比較して大きな値動きをしているのがわかると思います。
価格の変動が大きい
コロナショックでもお分かりの通り株/投資信託は容易に数十%の値動きがあります。
どんなに広く銘柄を入れた投資信託でも前回のコロナショックでは少なくとも20-30%の暴落をしています。
例えばS&P 500指数のコロナショックの際の値動きがこちらです。

約1ヶ月前後で3300前後であった指数が2250前後まで約30%以上の暴落をしています。
その後の経過はみなさんも知っての通り元々の数値まで回復し、最近では高値を更新しています。
上の画像の範囲だけを見るだけでも恐ろしいですよね。
私もこの時期VTIをメインにETFを保有していましたが、
投げ売りしたくなる気持ちを抑えてなんとかホールドし続けました。
スリル満点ですね。。。
資産増大のスピードが遅い
おおよそ年率3-7%程度がインデックスファンドのETFや投資信託のリターンと言えます。
数年単位で資産を倍増させるようなリターンは望めません(最もそのようなリスクは高すぎますが)。
結論
メリット
株式/投資信託の投資のメリットはインデックスファンドがあること
流動性が高く資産総額の高く流動性が高いこと
始めやすいこと
デメリット
レバレッジが掛けられない
王道のインデックスファンドへの投資は資産形成に時間がかかる
株式は値動きの変動が大きい
関連記事です
S&P 500やNASDAQ100について
リベラルアーツ大学の両学長がわかりやすく動画で解説しています。
第185回 【初心者向け】意外と説明できない「S&P500」の中身について分かりやすく解説【株式投資編】
第134回 コロナショックなんてなかった?米国株の超優良ETF「QQQ」について解説【株式投資編】
なおこの記事の記載はあくまでも筆者の見解ですので、読者の皆さんに当てはまる訳ではありません。
記事内の投資に関する最終決定は、必ずご自身の判断で行っていただきますようお願い致します。
本記事の内容にて判断を行い投資した場合に生じた損害について、筆者は一切責任を負いかねます。
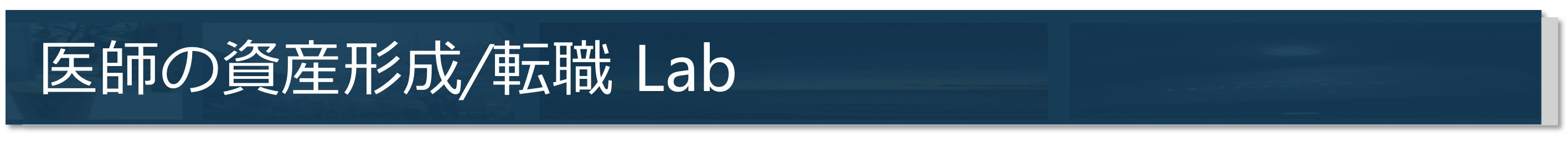






コメント